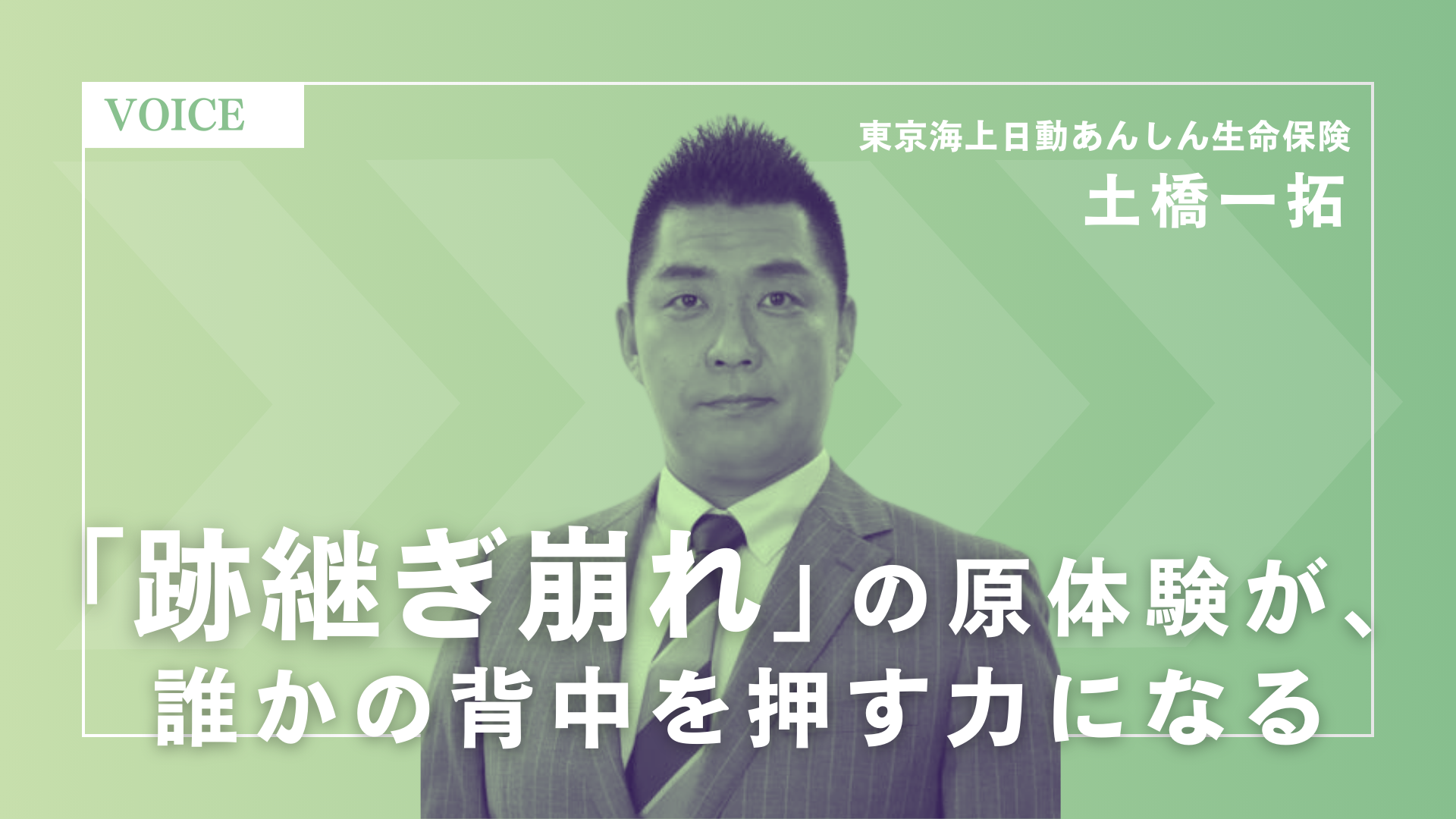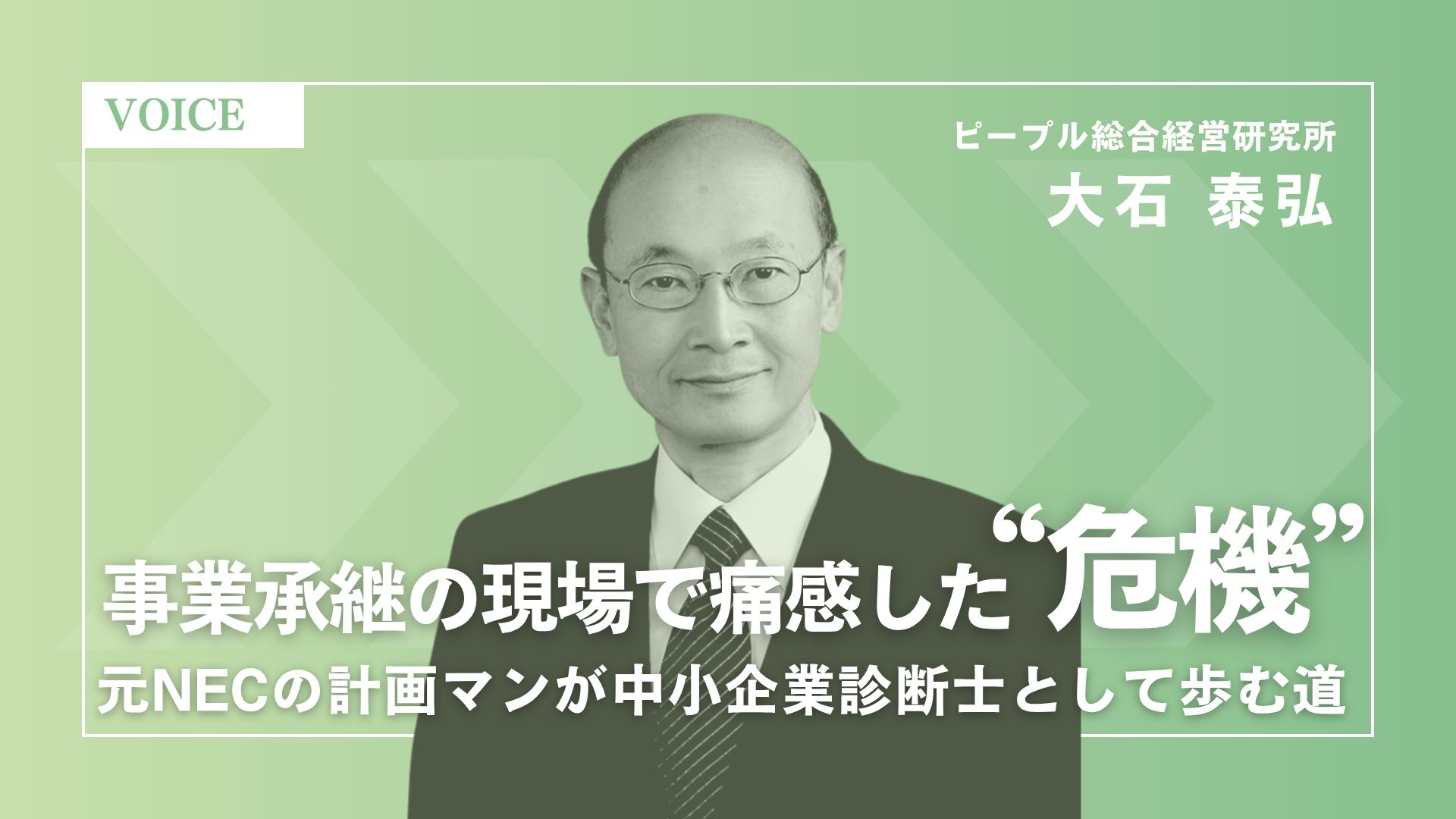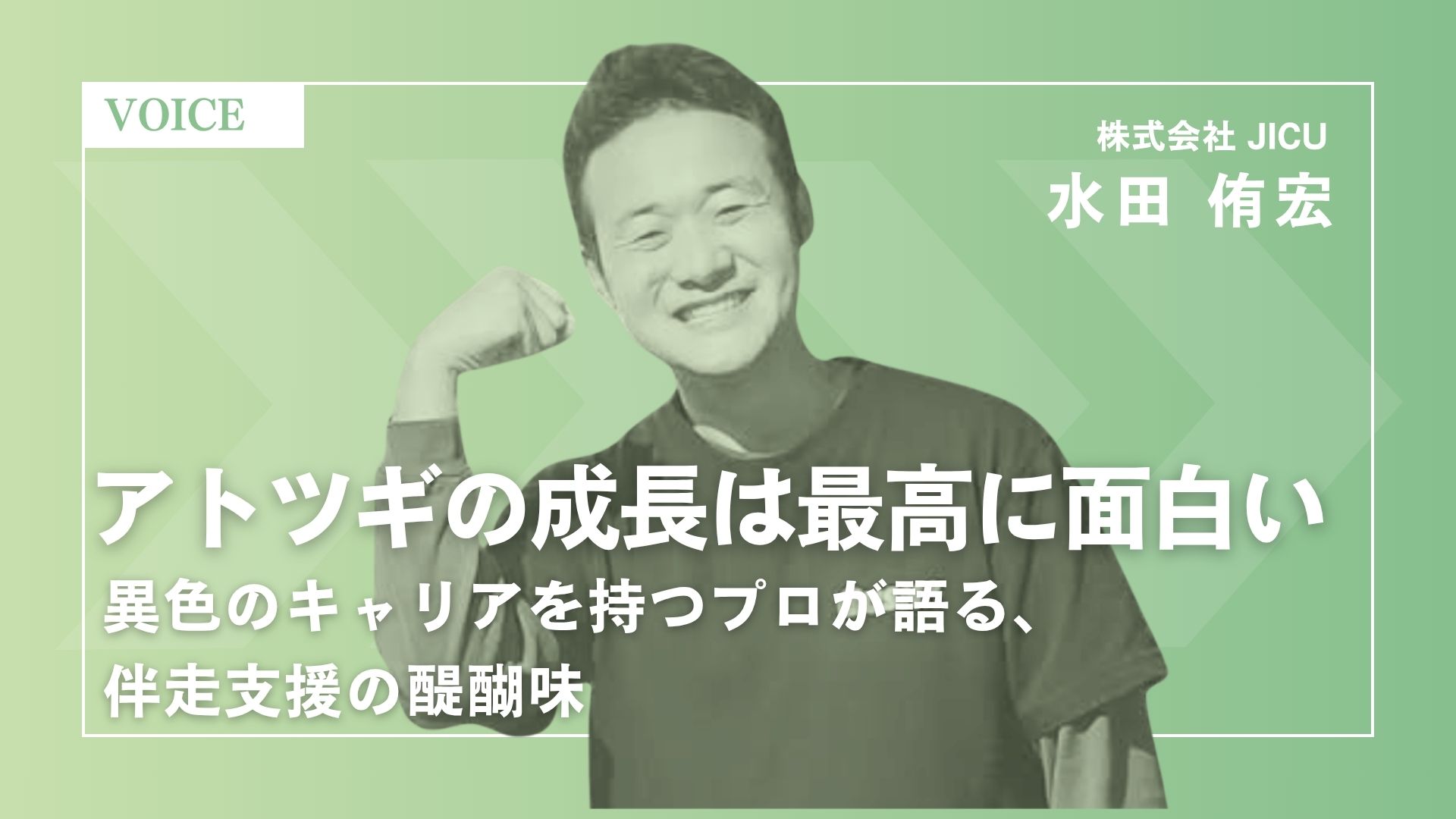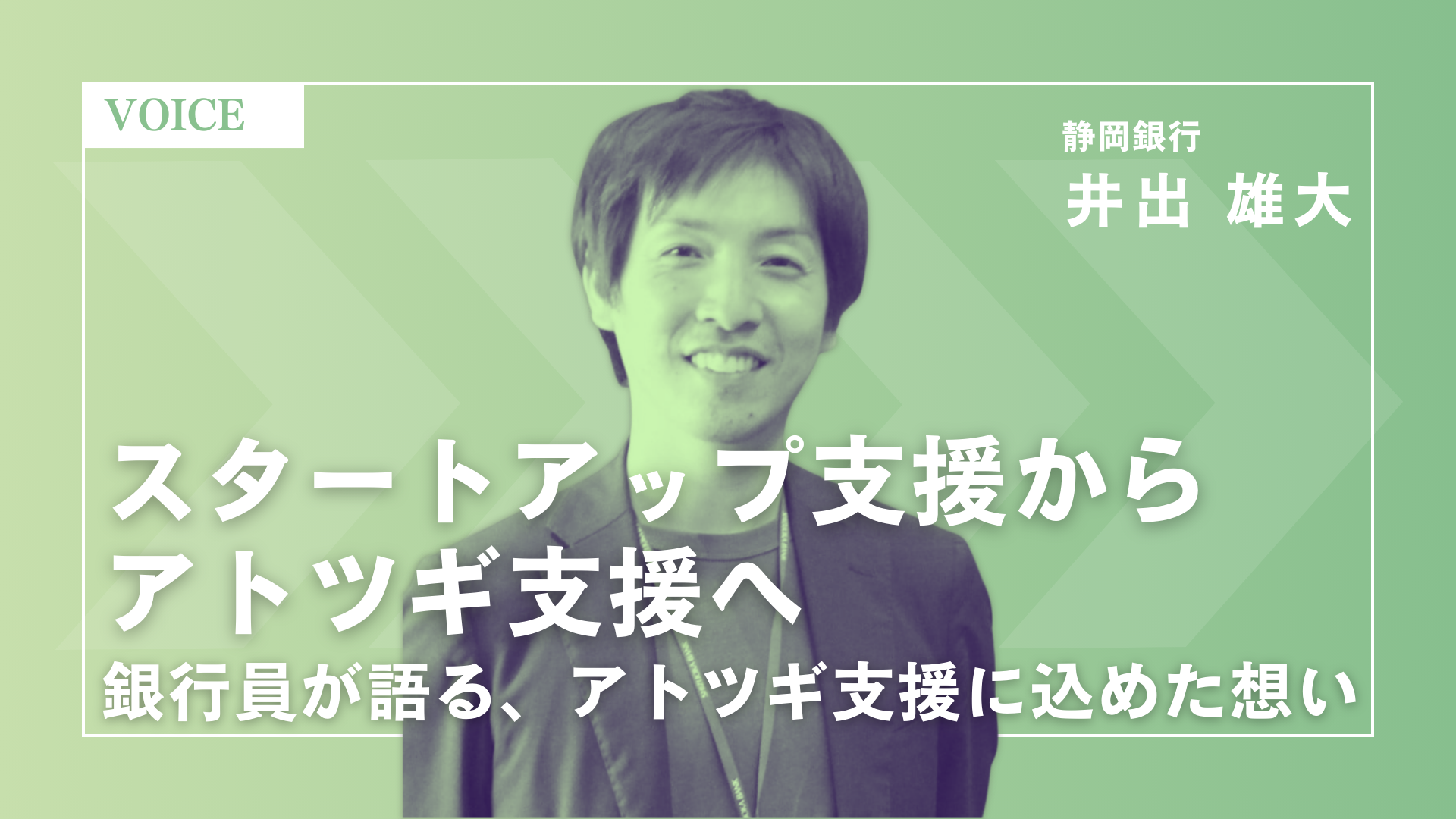Profile
ドバリン
さん
中小企業診断士
東京海上日動あんしん生命にて法人向け保険営業に従事しながら、中小企業診断士としても活動するビジネスパーソン。実家が農家だった自身の経験から、「お金で苦しむ経営者を支えたい」との思いで診断士資格を取得。近年は、後継者支援にも力を注ぎ、ファミリービジネスの組織づくりに寄り添う存在を目指している。

現在の仕事について
——今、どのようなお仕事をされていますか?
はい、私は東京海上日動あんしん生命という保険会社で、法人のお客様向けに生命保険の営業をしています。それに加えて、中小企業診断士の資格を活かして、補助金申請の支援や営業支援、マッチング、組織づくりなど、幅広いサポートも行っています。
特に最近は、事業承継に関するご相談が増えてきました。親御さんと後継者の間に立って、これからの組織体制をどう作っていくか、後継者が何をやりたいのかを一緒に考え、社員さんたちに伝えていく。そんな役割を担う機会が多くなっています。
中小企業診断士を目指したきっかけ
——診断士の資格を取ろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか?
実は、私の実家は農家だったんです。昔ながらの農家って、トラクターやコンバインを買うときに、近所同士で連帯保証をし合う文化がありました。ですが、そのせいで周りの農家さんが倒れていく中で、親も他人の借金を背負うことになり、自己破産寸前まで追い込まれたことがありました。
幸い、何とか持ちこたえることができて、今も両親と弟夫婦が農業を続けてくれています。でも、当時私はまだ大学生で、何の力にもなれなかった。その無力感がとても悔しかったんですね。
だからこそ、「お金で苦しむ経営者の力になりたい」と強く思うようになり、中小企業診断士の資格を取ろうと決意しました。
保険の仕事を選んだ理由
——保険を選ばれたことにも、その原体験が関わっているのでしょうか?
はい、すごく関係しています。大学を出た直後は、弟の学費を稼ぐために先物取引の営業をしていました。当時は法律も今ほど厳しくなかったので、朝7時から夜11時まで、ひたすら電話をかけ続けるような日々でした。
そんな日々を経て、30歳のときに大学のアメフト部の先輩から声をかけられたんです。「これまで攻めの営業ばかりしてきたなら、今度は守りの仕事も学んでみないか」と。ちょうど父が連帯保証で苦しんだとき、心労で倒れてしまったこともあり、保険の大切さを身をもって知っていたので、「守り」の意味がすっと腑に落ちました。
それで今の保険の仕事に飛び込んだ、という流れですね。
保険の仕事に感じたやりがい
——実際に保険の仕事を始めてみて、どんなやりがいや手応えを感じましたか?
前職の先物取引では、取引を始めても波が激しく、長く続くお付き合いが難しかったんです。でも保険は基本的に長く続くものなので、続ければ続けるほど信頼が積み上がっていく実感があります。
もう15〜16年この仕事を続けていますが、年月とともに、自分自身も成長し、お客様との関係も深まっていく。それがとても嬉しいですし、「寄り添う」というスタンスが自分に合っていると感じています。
アメフトとの出会いと秋田での青春時代
——アメフトも大学から始められたとか?
そうなんです。秋田出身で、能代高校という学校に通っていました。隣には超名門の能代工業高校があって、バスケの盛んな地域だったんですよ。私もバスケットボールをやっていました。
でも、バスケってちょっと触れただけでファウルを取られるじゃないですか。大学に入ったとき、アメフト部の先輩に「アメフトなら触れてもファウルにならないよ」と誘われて(笑)。そこからアメフトを始めました。
大学と社会人で2年ほどですが、本当にいい経験でした。
アトツギ支援との出会い
——後継者支援に興味を持ったきっかけは何だったのでしょう?
最初のきっかけは「後継ぎサマーキャンプ」というイベントでした。後継者たちと、私のような支援者が車座になって語り合う機会があったんです。
これまで私は保険営業という立場上、主にトップの社長さんたちと接してきました。でも、後継者さんたちとじっくり話してみると、本当にさまざまな悩みや葛藤を抱えていることに気づかされました。
実は私自身も、農家の長男として本来なら跡を継ぐ立場だったんです。でも家業が借金問題に巻き込まれたことで、結局「跡継ぎ崩れ」になってしまいました。そんな経験もあって、後継者たちを支える仕事ができたらいいなと思うようになったんです。
認定サポーター講座を受けた理由
——そこから「後継ぎ支援認定サポーター講座」を受講されたのですね。
はい、ちょうど「後継ぎ甲子園」というイベントを知り、さらに支援者として関わる道を模索している中で、この認定サポーター制度の案内が届きました。 これまでは、現社長の意向をメインに支援してきましたが、実は後継者本人の気持ちややりたいことをちゃんとヒアリングできていなかったな、と痛感しました。講座を通じて、ファミリービジネス全体を見渡し、後継者本人にも寄り添う視点が必要だと気づかされたんです。
後継者支援の中で感じた「心理的安全性」の重要性
——後継者と社長、向き合い方の違いはどこにあると感じますか?
一番大きな違いは、「心理的安全性」の有無だと思います。
会社は基本的に現社長をトップに据えた組織です。そこに後から入ってきた後継者は、たとえ身内であっても、すんなりと受け入れられるわけではありません。チャレンジしたくても、社内に味方がいない。失敗しても、慰めてくれる人もいない。
そういう孤独な状況を目の当たりにして、まずは後継者が安心してチャレンジできる環境を整えることが、何より大事だと感じるようになりました。
アトツギ支援で目指すもの
——今後、どんな形でアトツギ支援に取り組んでいきたいですか?
この前、静岡の井出さんたちと後継者の集まりに参加したことで、より強く思ったんですが、
私が目指したいのは「後継者のための組織づくり」です。
外に出て、仲間を作ることももちろん大事。でも、最終的には自分の会社の中に味方を作り、信頼される存在になっていく必要があります。社内で後継者の地位を確立し、安心してチャレンジできる環境をつくる。そのために、一緒に伴走する支援をしていきたいと思っています。
実際に行っている組織づくり支援とは
——具体的には、どんなサポートをされるんですか?
まずは後継者さんが、職場の雰囲気を少しずつ変えていくリーダーになれるような支援をしています。たとえば、社員さんたちの不満や要望を集めるワンオンワンの面談や、無記名のアンケート調査を一緒に設計したり。
集めた意見をもとに小さな改善を重ねることで、「後継者が本気で会社を良くしようとしている」と社員さんたちに伝わるようにするんです。
また、社長とも事前に「こういう取り組みをします」という握りをして、場合によっては社長に厳しく当たってもらうようお願いすることもあります。後継者だけが特別扱いされているように見えないよう、筋を通した見せ方を意識しています。
サポートしたい後継者像
——どんな後継者と一緒に仕事をしていきたいですか?
自信が持てずに悩んでいる後継者さんを、特に支えたいと思っています。
親御さんが強烈なキャラクターで、言いたいこともなかなか言えない。周囲からは「社長の子どもでしょ?」という目で見られている。その理想と現実のギャップに苦しんでいるアトツギは本当に多いんです。
そんな後継者さんが、自信を持って一歩踏み出せるように、心理的安全性を整え、一緒に成長していけたらいいなと思っています。最初の相談はもちろん無料で、気軽に声をかけてほしいですね。
これから挑戦したいこと
——今後、さらに取り組んでみたいことはありますか?
教育の現場とアトツギ支援をつなげることにも興味があります。
私自身、教員養成系の大学を出て、高校社会科の教員免許を持っています。地方の地場産業と、若い世代の新しい発想が交わる場をつくれたら面白いなと思うんです。
たとえば、地元の中高生と一緒に地域産業の新しいアイデアを考えるワークショップを開くとか。アントレプレナーシップ教育の流れにもうまく乗せながら、アトツギというリアルな生き方にも触れてもらえたら、日本全体がもっと元気になる気がしています。
最後に、支援を考える人たちへのメッセージ
——最後に、ドバリンさんと同じように支援を志す方々へメッセージをお願いします。
後継者支援って、実は金融機関や行政、士業の方々にもすごくチャンスがある領域だと思っています。
銀行さんにとっては、地盤のある企業の新規ビジネスを応援することで、融資や取引のチャンスが広がる。保険もリスクマネジメントの面で関われる。行政だって、縦割りを超えた地域活性化に繋がるかもしれません。
中小企業診断士の方々にもぜひ注目してほしいですね。幅広い知識を活かしながら、後継者に寄り添う支援ができるはずです。
そしてもう一つ。私は「跡継ぎ崩れ」だったからこそ、今支援する側に立てています。同じように悔しい思いをした人たちも、一緒に輪を広げていけたら嬉しいです。アトツギたちが安心して未来にチャレンジできる環境を、一緒につくっていきましょう。