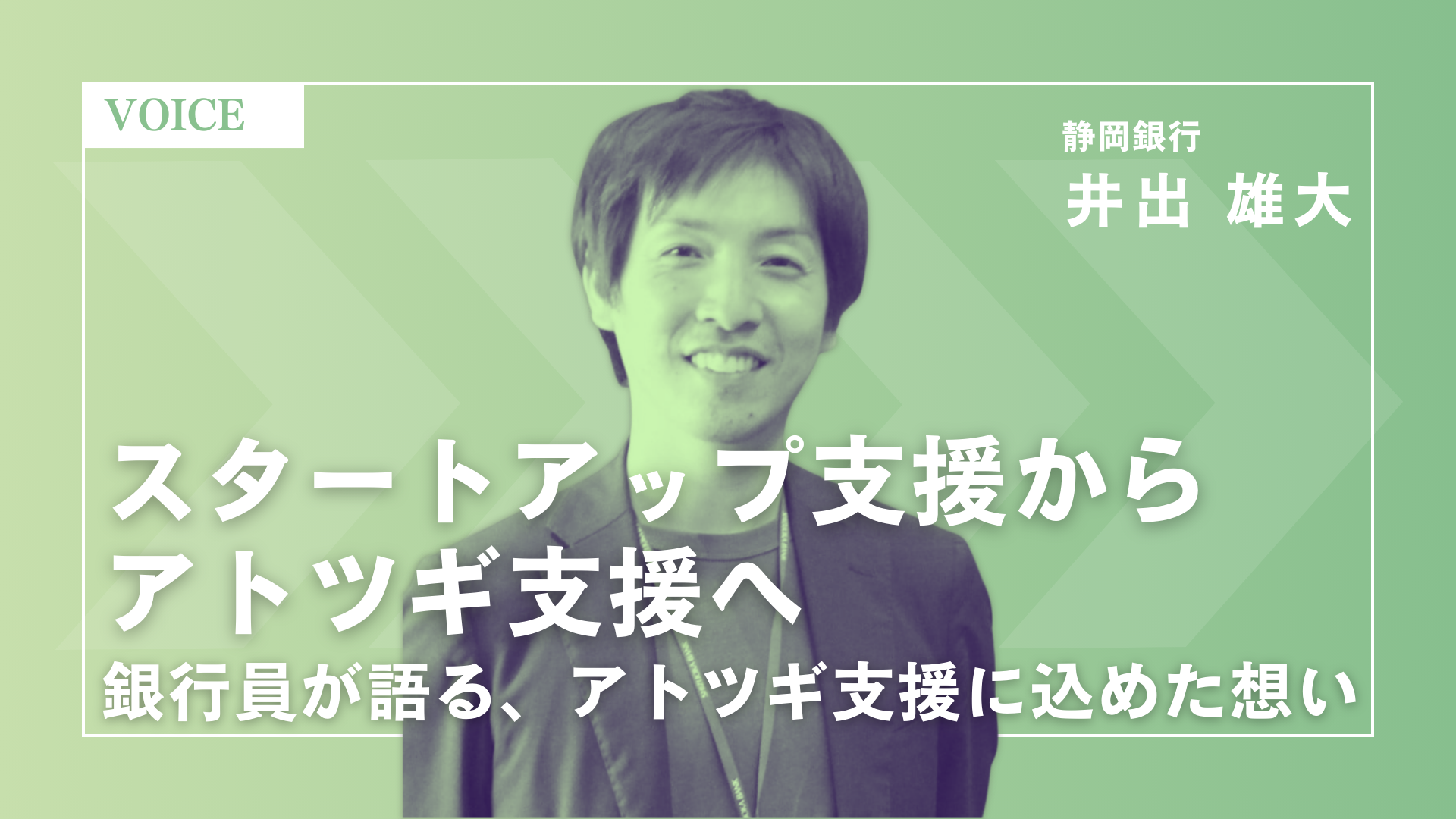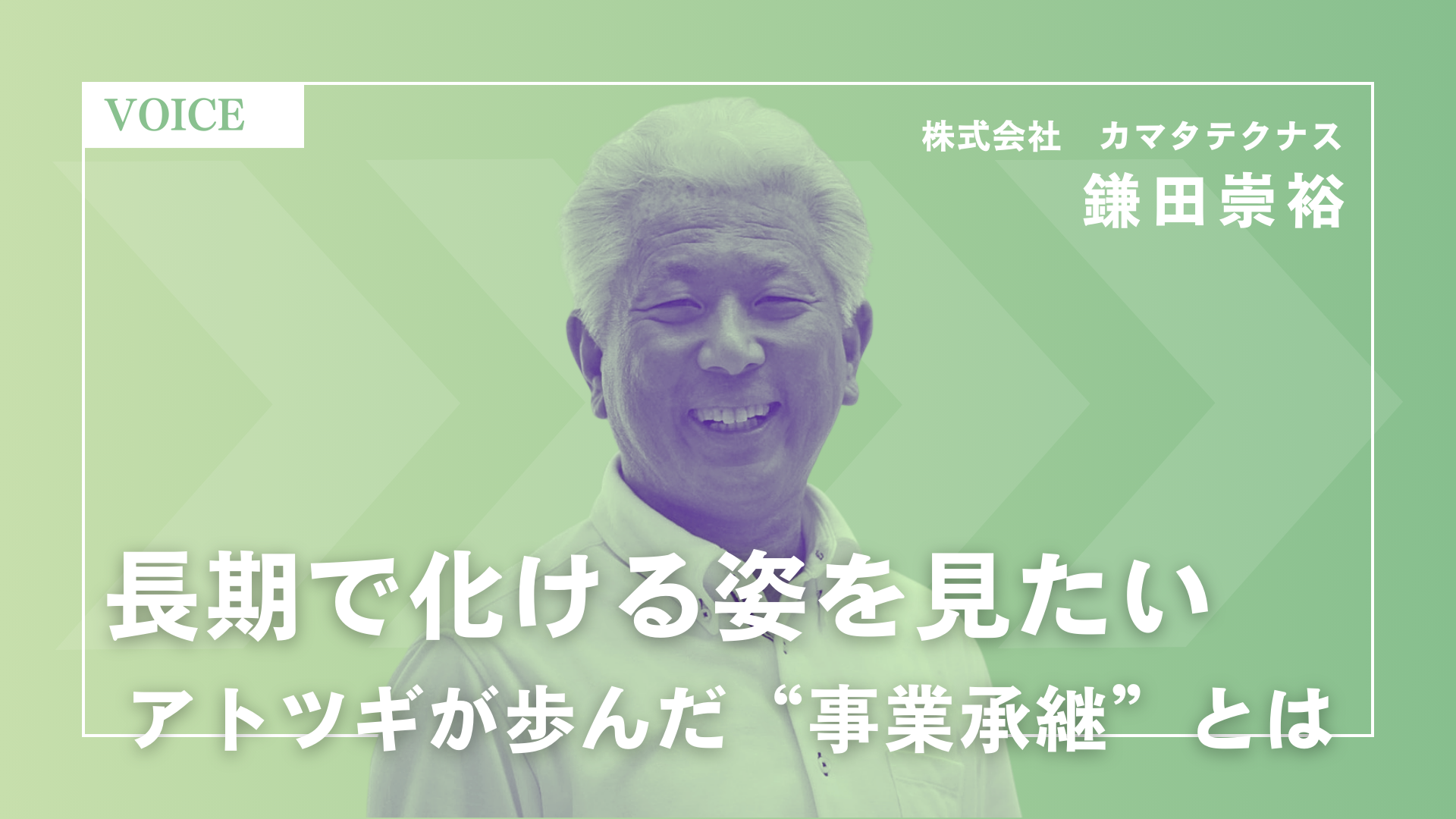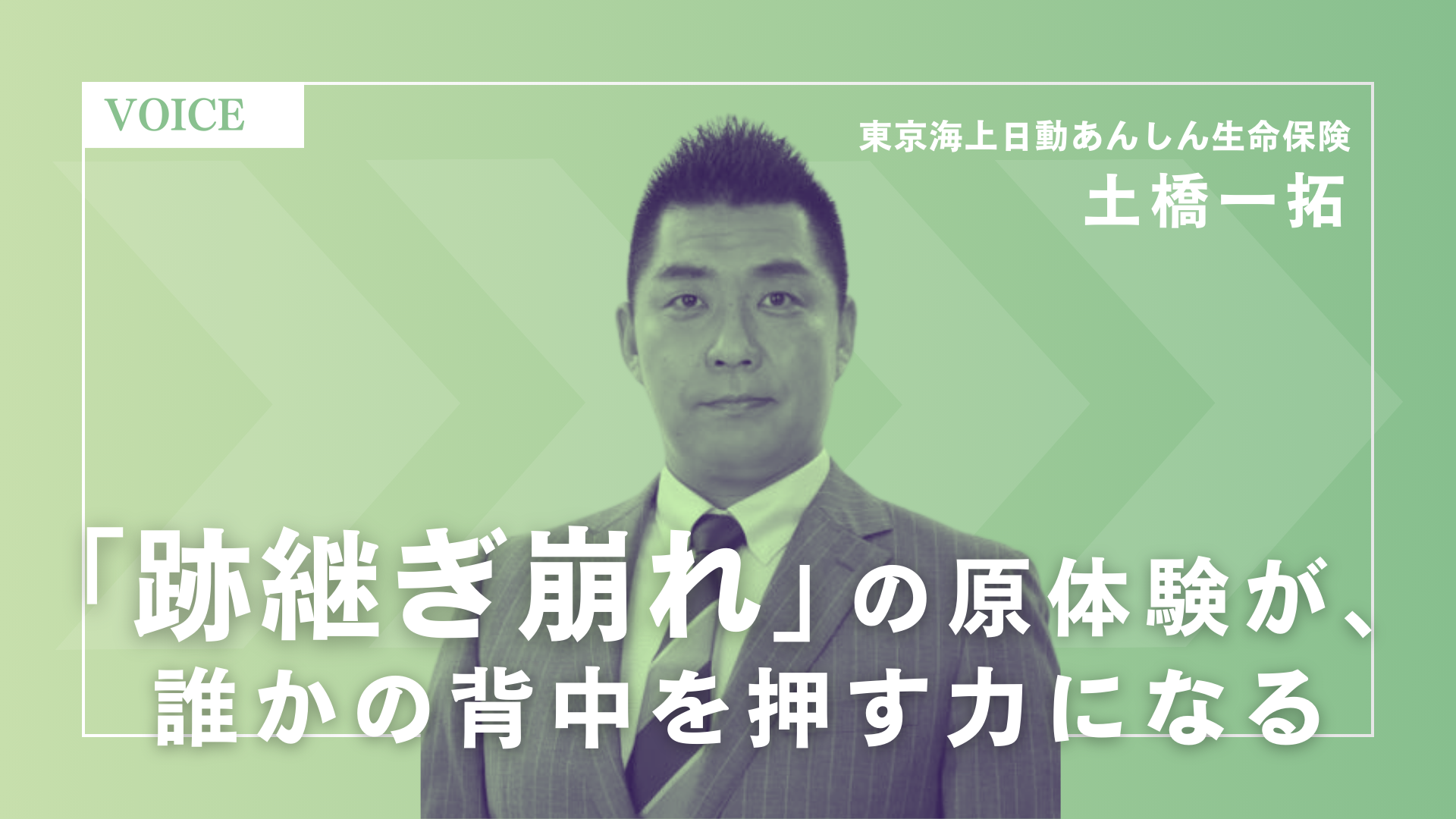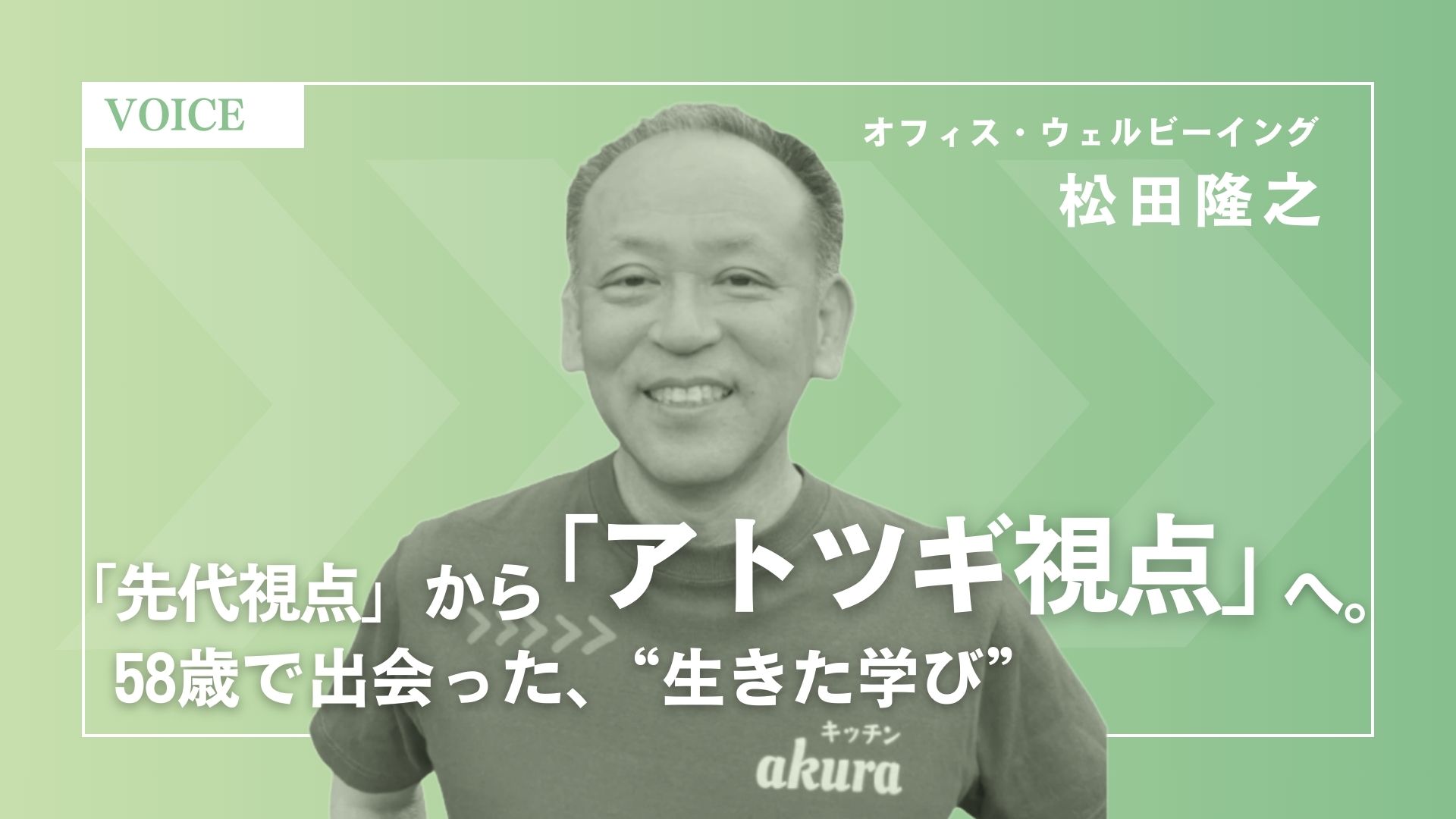Profile
ライナス
さん
課長
静岡銀行・地方創生部に所属し、地域に根ざしたスタートアップ支援や新規事業の創出に携わっている銀行員。自身も静岡出身で、地元愛と現場感覚を武器に、地域経済の未来を見据えた活動を続けている。
スタートアップ支援を通して出会った「アトツギ」たちに惹かれ、今では静岡県内でアトツギ支援の場づくりにも注力中。彼の語る「支援者としての在り方」には、銀行員として、そしてひとりの地域の担い手としての強い想いがにじんでいた——。

地域を元気にするために、銀行の立場からできること
——現在、どのようなお仕事をされていますか?
静岡銀行の地方創生部という部署に所属していて、「地域をどう元気にしていくか」ということをミッションに掲げて、さまざまな事業を企画・推進しています。
具体的には、地域に根ざしたスタートアップの支援や、地元企業と技術系スタートアップのマッチングを担当していて、「地域にイノベーションを起こし続けるにはどうしたらいいか?」を考えながら動いています。イベントを通じて出会いの場をつくったり、プロジェクトを企画したりと、地域の未来を見据えた取り組みに挑戦しています。
地元・静岡への想いが、キャリアの選択を導いた
——銀行を選んだきっかけは何だったのでしょうか?
正直に言うと、もともと銀行業界に強い憧れがあったわけではないんです。大学は東京でしたが、就活中にふと静岡の企業を調べるようになって。ある日、清水エスパルスの試合を観に行ったとき、サポーターが「清水!」と地元の名前を叫んでいる姿に強く感動して、「地元って、こんなにも応援される存在なんだ」と感じました。
その体験が、自分の地元・静岡への想いを再確認するきっかけになって、東京での就活から一転、地元企業への就職を決めました。だから、銀行というよりも「静岡で働きたい」という気持ちが先にあったんです。
スタートアップ支援から見えた、地方での課題感
——スタートアップ支援を続ける中で、アトツギへの関心はどう芽生えたのですか?
スタートアップ支援の現場では、東京のような都市部とは違い、地方には「ゼロイチで急成長するスタートアップ」には向かない側面もあると感じていました。実際、テックビートのようなイベントを通じて接する起業家の多くが、成長できるなら場所を選ばないというスタンスだったんですね。
一方で、自分は「地域で根ざし、価値を生み出す挑戦」を応援したいと思っていました。そんなときに出会ったのが、いわゆる“アトツギ”として挑戦している人たちです。彼らは地元を離れず、地域資源を活かしながら事業に取り組んでいて、「この人たちこそ、地域に必要な存在なんじゃないか」と感じたんです。
アトツギ支援という、新しいチャレンジ
——実際にアトツギ支援に取り組むようになって、どんなことをされていますか?
ここ半年くらいは、「アトツギ甲子園」のプレピッチ支援やイベント企画などを通じて、静岡県内のアトツギたちを支える場づくりに注力しています。具体的には、壁打ち相手とのマッチングや、模擬ピッチ会の開催など、挑戦の機会を整える活動ですね。
また、挑戦したアトツギが次の世代につながっていくような「学びの循環」を意識したイベントも企画しました。地域に「挑戦者がいる」という事実をもっと広めたいという思いもあります。

一人ひとりに寄り添うために、サポーター制度を受講
——アトツギ支援認定サポーター制度を受講しようと思ったきっかけを教えてください。
場づくりや人をつなぐことはある程度できていたのですが、個人としてアトツギと真正面から向き合ったとき、自分に何ができるのか……その問いには答えきれない感覚があったんです。
だからこそ、体系的に知識を得て、個々の課題に向き合えるようになりたいと思いました。同じ志を持つ全国の支援者とつながって、切磋琢磨できる環境に身を置きたかったというのも理由の一つです。
加えて、ベンチャー型事業承継さんの考え方や活動にはもともと強く共感していて、「ここがやっていることなら、間違いないだろう」という信頼もありました。
「家族」や「感情」に向き合うという視点の発見
——実際に講座を受けてみて、印象に残ったことは?
銀行員としての経験から、株式や経営の話などはある程度理解していたつもりでした。でも、アトツギの世界はそれだけでは語れない。「感情」や「家族との関係」といった、数値では測れない要素がすごく大きいんですよね。
講座では、そういったリアルな背景に深く触れることができました。表面だけを見ていては見落としてしまうような「本当の課題」に気づけるようになったことは、大きな学びでした。
今でも実際に伴走支援をしているわけではないのですが、イベントなどでアトツギと話すとき、自分の言葉の届け方や、相手の気持ちをどう汲み取るかについて、意識が変わったように感じます。
守りたいのは「価値を再発見しようとする姿勢」
——支援していきたいアトツギ像について、どのように考えていますか?
自分は「地域」という視点をすごく大事にしています。たとえば、すでに価値が失われつつあるものを、もう一度光を当てて守ろうとしている人——そういう姿勢に心から惹かれます。
業種や規模は関係ありません。銀行という組織の立場からすると「もっと大きな成果を」と求められることもありますが、自分が応援したいのは、地道でも真摯に地域と向き合っている人です。
また、そういうアトツギは往々にして孤独を抱えていることも多く、「一人じゃないよ」と伝えることが、自分にできる大切な役割だと思っています。安心できる場所をつくる。だからライナスという名前も、実は“安心”から来ているんです。
「事業につなげる」その先にある未来へ
——アトツギ支援をこれからどう発展させていきたいと考えていますか?
アトツギ甲子園などの取り組みは大きなきっかけになりますが、それを“その後”につなげていくことがとても大切だと感じています。
10人いれば10通りの事情があるアトツギに対して、「ビジネスとしてどう成立させていけるか」という部分まで踏み込んで伴走できるようになりたい。社会に還元される形で事業を成立させるところまで支援したいんです。
同時に、イベントなどを継続的に開催し、支援の流れを絶やさない仕組みも必要です。静岡がまた全国大会で結果を出せるように——そんな思いも込めて、挑戦者の輩出と、地元全体のエコシステム作りに力を入れていきたいです。

「銀行の立場をもっと使いたい」葛藤と覚悟
——銀行員という立場が活動にどう影響していますか?
実は、銀行の中でこの活動が十分に理解されているかというと、まだまだです。現状では「小さな取り組み」と見られている部分もあります。でも、自分は「銀行の持っているリソースこそが、アトツギ支援に大きな力を発揮できる」と信じています。
だから、いずれは組織としてもこの動きを広げていけるよう、今はまず自分ができることをやるしかない。説得や仕組み作りもこれからの課題ですね。地域に根を下ろす銀行だからこそ、地元の挑戦者を後押しする存在になれるはずだと思っています。
「応援する存在でありたい」ライフワークとしての支援
——支援者として、どんな存在でありたいと思いますか?
アトツギの多くは、実は強い想いを抱えているのに、それを外に出せずにいることが多いんです。「親の言葉に縛られている」「引け目を感じている」「挑戦が怖い」——そういった葛藤と向き合いながら一歩を踏み出そうとしている人たちです。
自分は、そんな人たちが「踏み出すきっかけ」となれる存在でありたい。背中を押す太陽のような存在でありたい。実際にビジネスを大きくすること以上に、「あの人がいたから始められた」と思ってもらえることのほうが、自分にとっては大切です。
この支援は短距離走ではなく、長い時間をかけて向き合うもの。自分のライフワークとして、たとえ部署が変わっても、形を変えて続けていくつもりです。
これから支援を始める人へのメッセージ
——これからアトツギ支援に関わってみたい人へのメッセージをお願いします。
アトツギって、実はものすごくリアルで、熱くて、やりがいのある支援対象です。地域金融機関にいる人なら、きっと誰しもが「地元の役に立ちたい」と思って入ったはず。その初心を思い出してほしいなと思います。
支援は何も大げさなことじゃなくて、イベントを見に行く、一言応援のコメントを送る、それだけでも力になります。静岡の取り組みも、ぜひ見に来てください。一緒に、楽しい地域の未来をつくっていきましょう。