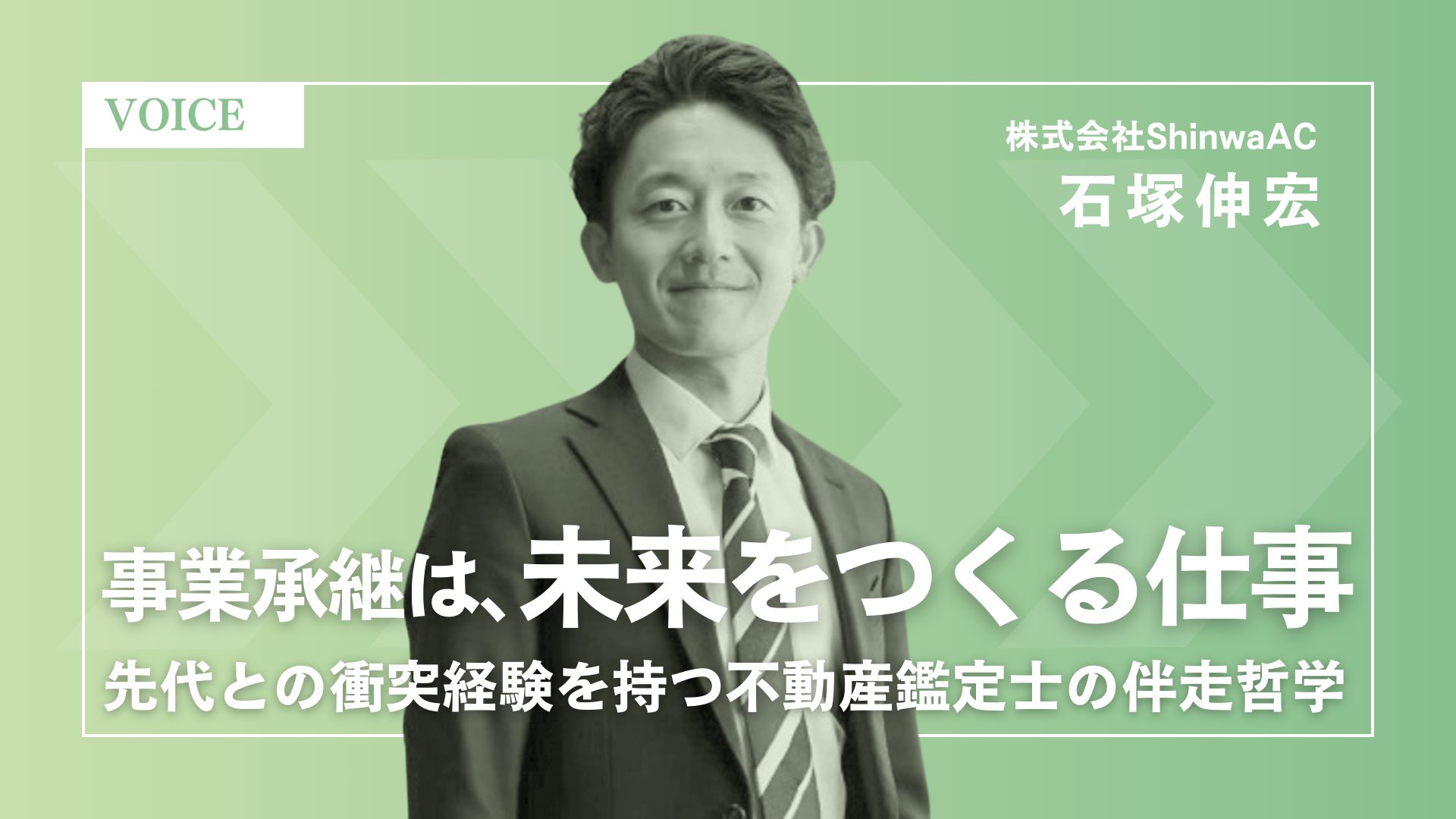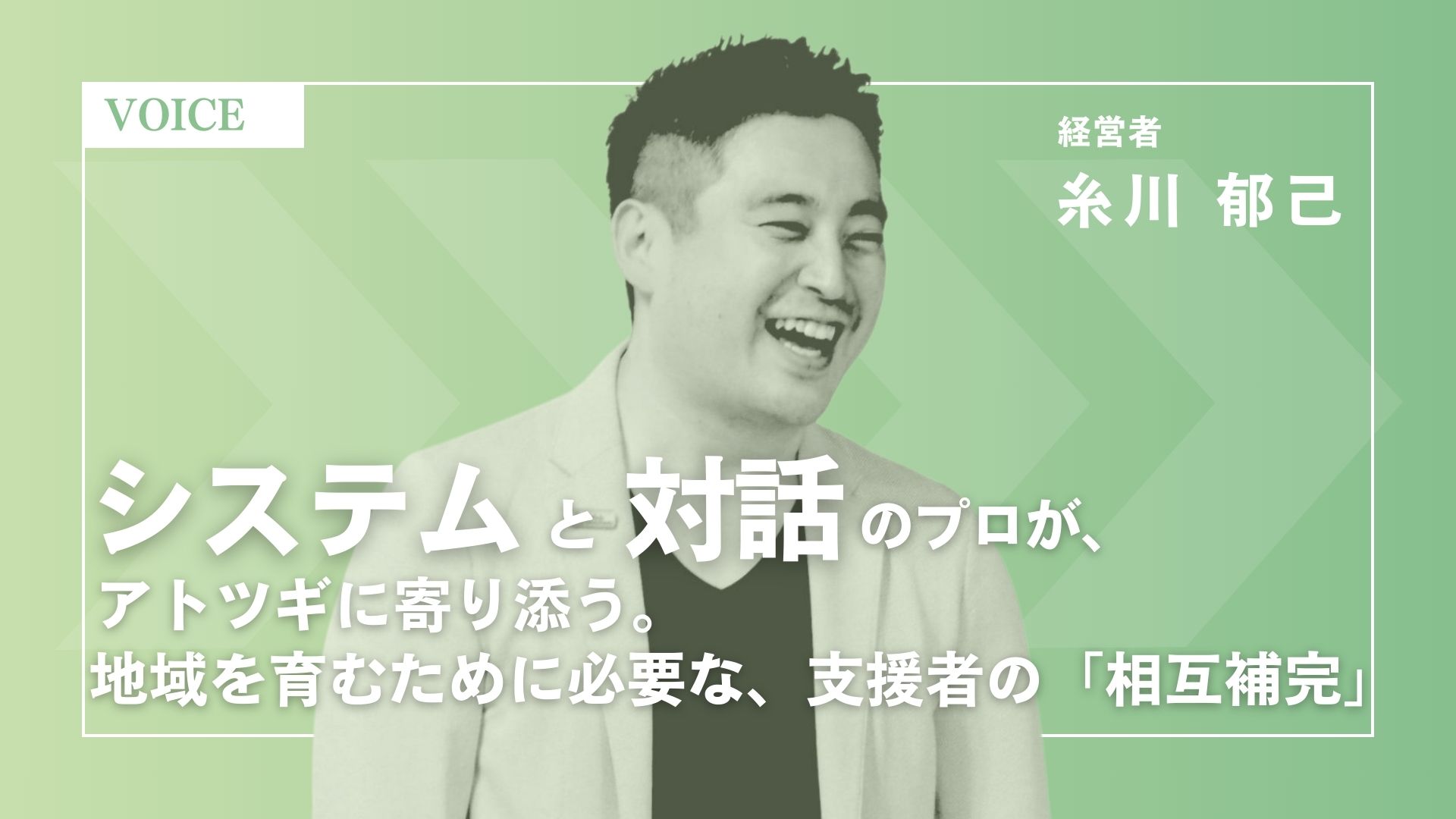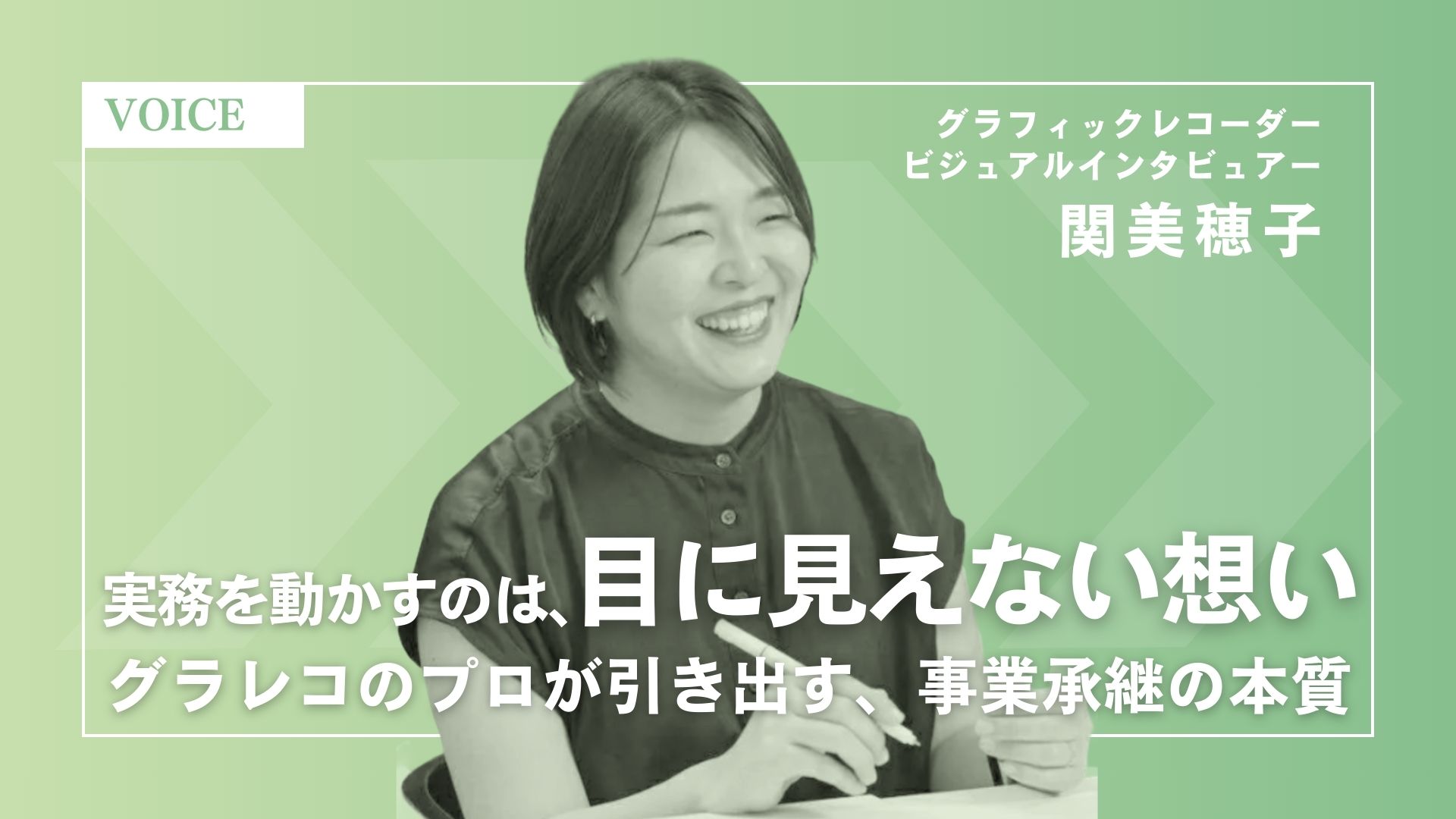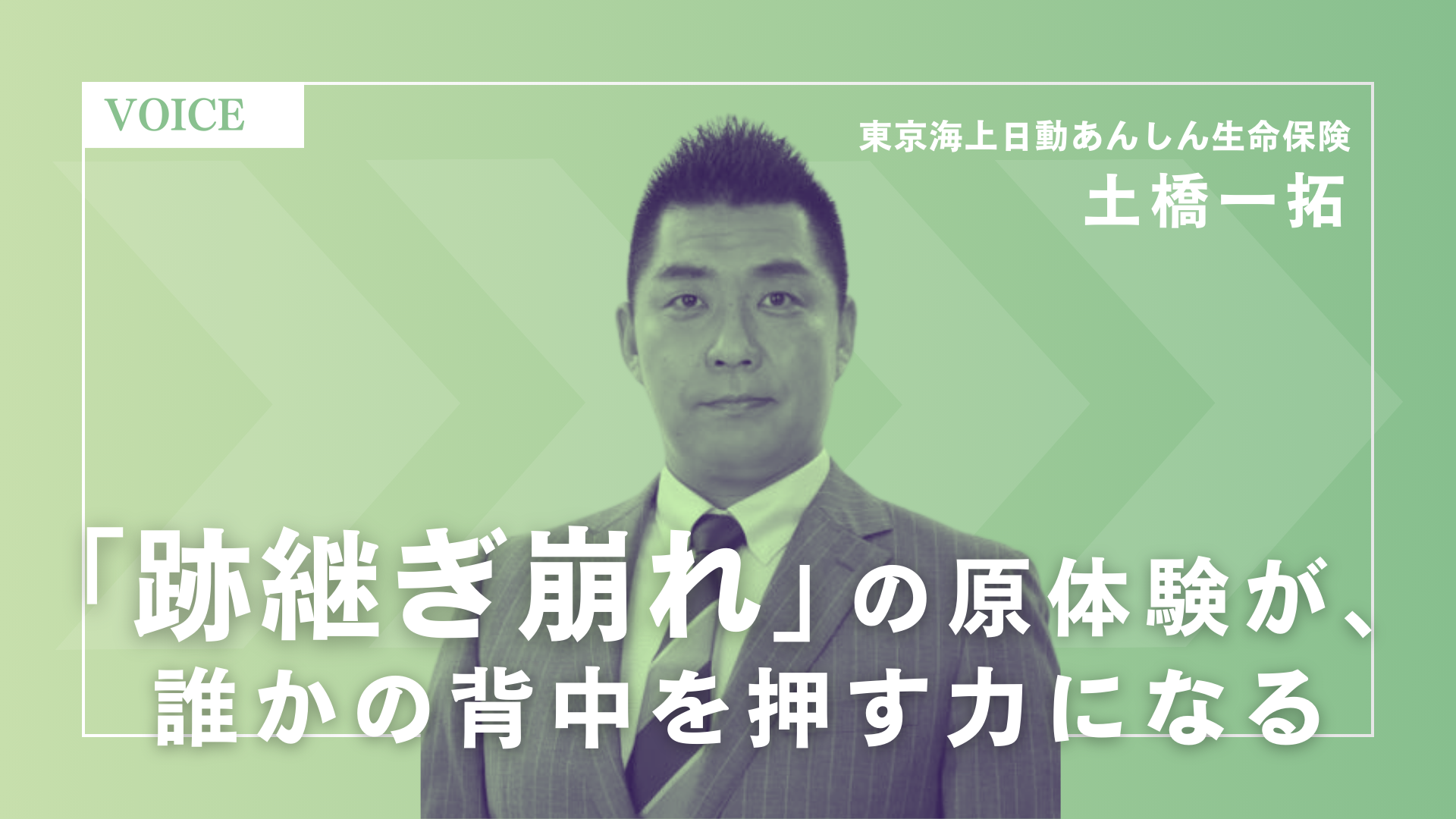Profile
エリック
さん
弁護士
富山県出身の弁護士、エリック。
大阪の弁護士事務所で10年以上、企業法務や相続案件に携わり、M&Aや相続、事業承継の現場を数多く経験してきた。
パートナー弁護士としても経営に参画し、現在は神戸に拠点を移し、中小企業の現場にさらに深く寄り添う活動を続けている。
「専門知識を武器にするだけでは、事業承継の課題は解決できない」と語る背景には、弁護士として積み重ねてきたリアルな現場感がある。

法律家が見た事業承継のリアル
── これまでどのようなお仕事をされてきたのかお聞かせください。
もともと大阪の法律事務所で、M&A案件を多く担当していました。M&Aは日常業務の一部という感じでしたね。
弁護士になってから7年間、アソシエイトとして実務を経験し、その後はパートナーとして3年間、事務所の経営にも携わりました。
M&Aと並行して力を入れていたのが相続です。弁護士になってから相続にかかわる法律・税制の大きな改正が何度もあったのですが、法制度改正のキャッチアップがとても大変でした。
ならばと、大阪弁護士会の「遺言・相続センター」という相続分野の専門部署に参加して法改正に関わる情報にアンテナをはり、そこから7年間ほど相続分野を専門的に扱うようになりました。
法律の専門家として、数々の案件に立ち会ってきた中で強く感じていたのは、「もっと手前で防げたはず」というもどかしさです。
法廷で争うまでこじれた紛争は、時間もコストも膨大にかかります。「不毛な争い」を未然に防ぎ、事業を健全に次世代へ引き継ぐことの重要性を痛感してきました。
相続とM&Aの間に横たわる共通の課題
─ 法律家として見ると、M&Aも相続も、そしてアトツギ支援もすべて地続きなんですね。
そうですね。特に中小企業の案件を扱っていると、M&Aも親族内承継も、そしてその先の事業再生や倒産といった分野も、私の中ではすべて地続きなんです。
たとえば後継者がいないから、会社を売却するという話もあれば、そのまま廃業・倒産するという話もあります。事業承継を考える中で、遺言や相続が複雑に絡む承継の話もあります。
やっていることは違いますが、意思決定の場面では共通する部分が多い。だから、全く関係のない分野を扱っているという感覚は、あまりないんです。
弁護士として見てきた、感情が絡んで長期化する紛争
── アトツギ支援に関わろうと思った背景には、弁護士として見てきた「不毛な」事例があったと伺いました。
まさにその通りです。弁護士のところに来る案件は、もうすでに揉めに揉めているものばかりですから。
たとえば、親族内承継でも、株式を順次渡していったものの、半数を超えたところで息子が先代を解任して会社を乗っ取ろうとして、そのまま、泥沼の紛争に発展したケースもあります。
中小企業の内紛案件や相続案件は、長引くことで有名なんです。弁護士になって10年以上になりますが、この10年間ずっと携わっている案件もありますから。承継や株に関わるトラブルは総じて解決までの道が長いんです。感情論と法律論が複雑に絡み合い、最終的にはどちらかが疲れ果てて諦めるまで続く。
会社の紛争も相続もとにかく長いので、私は「もっと手前で、こういう無意味な消耗戦は防げたはずなのに」と常々感じていたんです。そうした「不毛な消耗戦」をなくしたいという思いが、アトツギ支援に深く関わるようになった一番の理由です。

法律だけじゃない。「適応課題」を解決するアプローチ
── アトツギ支援認定サポーターの存在は、どのように知られたのですか?
大阪弁護士会の活動をする中で、ベンチャー型事業承継のことを知りました。主宰するイベントに参加したこともあって、存在はずっと前から知っていました。
DMが届いたとき、一番心惹かれたのは、「法律とか、専門的なところだけじゃないな」という点でした。
弁護士が事業承継を語る時、どうしても法律からの目線で物事を見ます。でも、実際の現場ではもっと大局的な視点が必要だと感じていたんです。
私は事業承継の現場に立ち会ってきて、法務や税務的に答えのある「技術課題」よりも、答えのない「適応課題」の方がよっぽどコアな問題だと感じていました。
法律や税務の観点では、様々な問題を、いわば「答えがある問題」を扱う技術課題として認識しがちです。しかし、実際の承継の現場では、法務や税務的に正しくても、それだけで解決しない問題が多くあります。親子間の感情的なもつれやコミュニケーション不全といった、答えのない「適応課題」が核心にあることが多い。だからこそ、弁護士の枠を超えた関わり方が必要だと強く感じています。
法律を超えて見えた「ファミリーガバナンス」の力
── 講座を受講してみて、何か発見や印象的なことはありましたか?
ワークショップ形式で、多様なバックグラウンドを持つメンバーの経験を聞けたのは、非常に良かったです。同じ課題に向き合っても、それぞれの切り口が違っていて、「こういう考え方があるのか」と発見の連続でした。
特に印象的だったのが、「ファミリーガバナンス」という概念です。法的な拘束力はなくても、家族間の共通認識を作ることで、事業承継が円滑に進むという話を聞いて、最初は正直「大きなコストをかけて、法的に意味のないものを作ることに、何の意味があるんだろう」とネガティブに感じていました(笑)。
でも、後から自分の中で咀嚼して、「法律的な正解がなくても、そういう温度感のものが、むしろ物事をうまく進める上で重要なのではないか」と考えるようになりました。
弁護士は法律の物差しで測ろうとしますが、それだけではない、もっと広い視点があるということを、改めて認識できました。
また、アトツギと実際に接点を持てるということも価値を感じましたね。私の普段の活動でアトツギと直接つながることはなかなかありません。彼らの生の声を知れたことは、大きなメリットでした。。

一歩踏み出した先にあった、社会貢献という道
── 今はご自身でも団体を立ち上げて、活動されているそうですね。
はい、私は「百年企業を残す」という思いで、弁護士や税理士、社労士、中小企業診断士が集まる一般社団法人事業承継コンサルティングファームを立ち上げました。
今、中小企業の倒産件数が肌感覚でめちゃくちゃ増えています。これは、構造改革からコロナ禍まで続いた政府の支援策が終わり、生産性を向上できない中小企業が淘汰される時代に入ったのだと感じています。
そんな淘汰の時代だからこそ、本当は残すべき価値のある事業を、法律だけではない多角的なサポートで守っていく必要がある。私たちが目指すのは、価値のあるものがただ消えていく「もったいない」状況をなくすことなんです。
この団体では、後継者選びのお手伝いをしたり、その後の事業承継計画の策定などの伴走支援を行っています。また、事業承継に関するセミナーや勉強会を開催したりしています。
個人的な活動としても3か月に1度、相続と事業承継をテーマに交流会を開催していて、弁護士だけでなく、他士業、保険金融や不動産の方も多く参加されます。その交流会に参加すれば、その場で、各専門家と支援チームをビルドできるようにしています。
私は、こうした活動を通して、専門家がそれぞれの強みを持ち寄り、「もったいない」をなくすためのチームを社会全体でつくっていきたいと考えています。
アトツギ支援の面白さは長期的な支援
── アトツギ支援認定サポーターには、どんな人が向いているとお考えですか?
認定サポーターの数を増やすだけなら、即物的な案件紹介につながると言えば飛び込んでくる人は山ほどいるでしょう。でも、この活動の価値は、そういうことではないと思うんです。
もちろん、交流を通じて仕事につながることもあるでしょう。しかし、この活動の一番の価値は、利益を追求するだけでなく、「自分の強みを活かして、本当に社会や誰かの役に立つ活動ができる」という自分の人生の価値観を大切にできることにあります。
アトツギ支援の面白さは、短期的な成果ではなく、長期的な関係を築いていけることだと思います。自分の人生として、どんな活動をしていきたいのかを見つめ直すことができる。これは本当に特別なことです。
未来のサポーターへ「人生をかけて、何をするか」
── 最後に、これからサポーターになる人にメッセージをお願いします。
とにかく、一歩踏み出してみてほしい。社会はどんどん変化していくし、じっとしているうちにチャンスが通り過ぎてしまう。だからこそ、「まずは動く」ことが本当に大事です。
一人では難しくても、仲間とならできることはたくさんある。地域で孤独に頑張っている方こそ、ぜひ全国の仲間とつながってほしい。アトツギ支援は、人生をかけて関われる、すごく面白いフィールドです。興味を持ってくださった方と、ぜひどこかでお会いできたら嬉しいです。